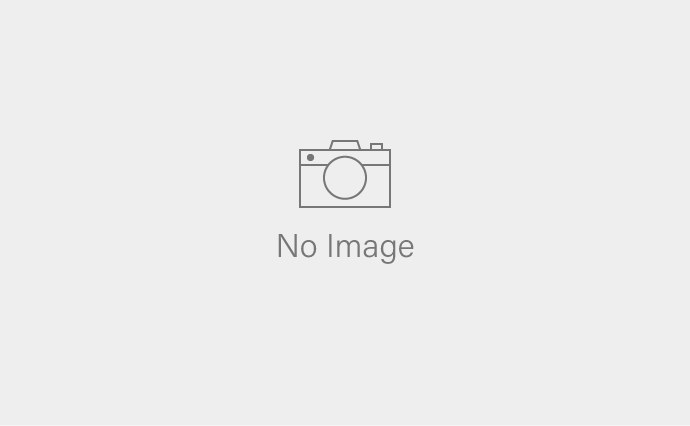中綴じ冊子で「小口が切れてノンブルが欠けた」「見開き写真が中央で食われて違和感」という相談は、毎年一定数やってきます。
原因はシンプルで、中綴じ特有の『のど逃げ(クリープ)』を前提に設計できていないから。
この記事では、発注者に説明するときの言い方、デザイナーと擦り合わせる数値の目安、社内で事故を潰すオペレーションまで、私の現場感でまとめます。
1. のど逃げ(クリープ)を30秒で
中綴じは、折り重ねた用紙の中心をホチキスで留めてから小口側を断裁します。束の中心ほど紙が外に膨らむため、断裁で中心に近いページほど小口を大きく切ることになります。これがのど逃げ(クリープ)。
結果、小口寄りの文字・ノンブル・飾り罫が切れたり、見開き写真の連続性が損なわれます。解決策は、(1)レイアウト上の安全エリア、(2)面付・断裁工程でのクリープ補正、(3)見開き要素の置き方の三位一体です。
2. 安全エリアのルール(まず“白線”を引く)
- 小口側:A4基準で6–10mmの“触ってはいけない帯”を設定。ページ数・紙厚が増えるほど10mm側に寄せます。
- のど側:テキストは3–5mm内側に。背割りをまたぐ細線・小サイズ白抜き文字は原則NG。
- 塗り足し:四辺3mmは中綴じでも不変。背景や写真は“実体”で延ばす(クリッピングで見かけだけ延ばすのは不可)。
現場では、この“白線の説明”が一番効きます。「小口に10mmの見えないガードレールを敷きます」と伝えると、非デザイナーの方にも伝わります。
3. クリープの“ざっくり式”と使いどころ
最大クリープの目安は次の通り(中心折丁で最大)。
最大クリープ(mm)≒(用紙枚数/2 − 1)× 紙厚(mm)
紙厚(mm)≒ gsm × バルク / 1000
※中綴じは 4ページ=用紙1枚。例:48p → 12枚。
例:48p/本文90gsm・マット(バルク0.90)
紙厚 0.081mm → 用紙12枚 → 最大クリープ ≒ (12/2−1)×0.081 = 0.81mm
この最大値を面付側で中心→外側に段階配分します(これが“クリープ補正”)。
ディレクター視点では、安全エリアは6–10mm確保、面付補正は0〜0.8mmの直線配分と明文化しておくと制作・工場の両方が動きやすいです。
4. 見開きデザイン:NG→OKの思考法
NG例
- 背割りにロゴ・人物の顔の中心・小さな文字をまたがせる。
- 0.25pt以下の極細線を連続させる。
- 白抜き細ゴシックを背近くに配置。
OKの置き換え
- ロゴは片側に寄せる/背中央で分断しない。
- 見開き写真は背から2–3mm外に主役を逃がし、背にかかる部分はテクスチャや無地にする。
- 線は太く、背近くは線間を広げる。
- 重要情報は小口10mmガードの内側へ。
営業としては、先方のレイアウト案を見た時点で**“背で割りたくない要素”を付箋で可視化して提案します。「安心して切れる配置」**への言い換えが肝です。
5. InDesignでの実務:任せる・やらないの線引き
- プリントブックレットの“クリープ設定”は便利ですが、面付けPDF入稿NGの工場も多い。基本は単ページPDF/X-4で入稿し、面付け側で自動クリープが安全。
- 例外として、社内一貫または同一工場固定で流す場合のみ、こちらで仮面付け→見た目検証まで行う運用も有効。
- ディレクターの私見:人間側の“見た目確認”を1回入れると事故が激減します(等倍プリントで背をテープ留め→擬似開き)。
6. 紙・ページ・サイズで変える“現実的な目安”
- ページ数:32p・48p・64pは別物と考える。48pを超えると小口ガードは8–10mmへ。
- 紙厚/バルク:上質・厚手はクリープ大。写真系カタログでマット110gsm以上なら10mm堅持。
- 判型:A5やB6の小型判は、同じmmでも相対比が大きく見えるため、情報を中央〜のど寄りに寄せるのが安全。
経営の視点では、ここを社内標準ガイドに落とし、見積り・スケジュール・校正の各テンプレに差し込むと、手戻りコストが目に見えて減ります。
7. 検収で見るポイント(社内外のすり合わせ)
- 小口10mm帯に情報が侵入していないか。
- ノンブル・柱は小口に寄りすぎていないか。
- 背割り上の要素(罫線・柄・写真の重要部分)が“違和感の少ない切れ方”になっているか。
- 等倍モックで、中心折丁→外側へめくりながら視認(中心ほど切られる前提で観察)。
お客様と話すときは、初回案件では紙でダミーを必ず作り、その場でめくります。口で説明するより、体感の共有が一番の説得材料です。
8. コミュニケーションの型(営業テンプレ)
先方への一言
「中綴じは中心に近いほど小口を多く切ります。小口側は10mm空け、背で割りたくない要素は片側に移すと“見たまま”に仕上がります。」
社内制作への一言
「この冊子は48p・90gsm。最大クリープ約0.8mm想定。小口ガード8–10mm、背近くの細線禁止。見開き写真は背から3mm逃がして配置を。」
工場への一言
「面付けで0→0.8mmの直線配分でクリープをお願いします。ゲラは折りチェック用に束ね見本で1部ください。」
9. いつ中綴じを諦めるか(判断のライン)
- 紙が厚い/ページが多いのに“開きの平滑”を求めると、コストの割に満足度が下がります。
- 48–60p・厚手系で違和感が強い場合は、無線綴じへ切り替え。背が出る分、情報設計がしやすくなるケースも多い。
- ここは提案力の見せ場。営業としては「目的に対して違う最適解がある」ことを丁寧に伝えます。
10. よくある失敗とワンポイント処方箋
- ノンブル欠け → 小口ガード**+2mm**/ノンブルはのど寄りへ移動。
- 見開き被写体の分断 → レイアウト替え or 背位置の“無地化”(柄を背で切らない)。
- 白抜き細ゴシックのかすれ → 太らせ+ボールド、背近くは黒地に黒文字などOP事故も併せて回避。
- 面付けPDF入稿でNG → 規定を確認し単ページPDF/X-4に戻す。クリープは工場側へ。
まとめ(私の“現場三箇条”)
- 白線を引く:小口6–10mm、のど3–5mm。
- 最大クリープを見積もる:48p×90gsmなら約0.8mm。面付けに前提情報として渡す。
- 見開きは欲張らない:背で割らない、割るなら“割っても破綻しない”配置にする。
営業・ディレクター・制作、どの立場でも判断の起点は同じです。「見た目の正解が、製造プロセスの正解に乗っているか」。その橋渡しができていれば、のど逃げは“怖くないテーマ”になります。今日の案件でも、まずは小口10mmのガードレールから引いてみてください。