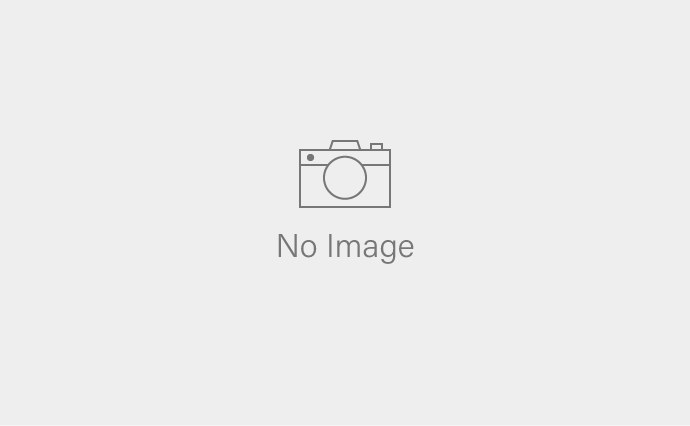この会社に来て20日目。
事務と専務から「営業車のエンジンが焼き付いて故障した。修理代はいくらです。」と報告を受けました。
「ディーラーからの点検の通知は来ていない。」やら、「あーだこーだ」私や社長には直ぐに報告が来ず、自分たちの責任、自社の責任だとなかなか認めない担当の姿に怒りは覚えませんが、会社の力がないなって感じました。
その営業車を使用する営業はどう感じているのでしょうか。
あたふたする姿は昨日見かけましたが。
車のエンジン焼き付けなんて、オイル交換のランプがついてから相当走らせないと焼きつかないのでは?
詳しい方、車の整備士さん教えてください。
ランプがついても忘れるような日々の仕事量だったのでしょうか。
何かその営業さんのランプがついていても無視し続けた理由を探しますが、見つかりません。
今朝社長に報告しましたが、「修理は認めない。他にも営業車はある。どうするかみておけ。」と指示を受けました。
私なら仕方ないことだから、修理して、社内の体制や上の指導・管理が足りていなかったから、営業車の扱いに関する会議を開いて、今後このようなことがないように取り決めを行うところでしたが社長は違いました。
私のこのやり方では優しすぎるなと反省しました。
叱ることも必要だなと。
教えてChatGPT
私
車のエンジン焼き付けってオイル交換ランプついてからも相当走らせないとならないよね?
チャッピー
エンジンの「焼き付き」は、オイル交換ランプが点灯したくらいではすぐには起こりません。ただし、仕組みを整理すると次のようになります。
オイル交換ランプの意味
- 最近の車にはオイル交換時期を知らせるランプ(インジケーター)があり、走行距離や経過時間、エンジンの使用状況などから計算して点灯します。
- このランプが点いても「すぐ危険」というわけではなく、あくまで推奨交換時期を知らせているにすぎません。
焼き付きが起こる条件
- エンジン焼き付きとは、潤滑が不十分になり金属同士が直接擦れ、摩擦熱で表面が溶着する現象です。
- 主な原因は以下です:
- 極端にオイルが減っている/漏れている
- 長期間オイルを交換せず劣化が進行(酸化・スラッジ・粘度低下)
- オイルポンプの不良などによる潤滑不足
つまり、単に交換ランプが点灯しただけで即焼き付くことはなく、そこからさらに長期間走り続け、オイル性能が極端に低下して初めてリスクが高まるという流れです。
実際のリスク感覚
- ランプが点いた状態で数百 km 〜 千 km 程度走っても、多くの場合すぐ焼き付きには至りません。
- しかし、オイルは熱や金属摩耗粉で確実に劣化しているので、エンジン内部の摩耗やスラッジ堆積が進むのは確実です。
- 無交換でさらに走り続けると、焼き付き・タービン損傷・オイル消費増大などの深刻なトラブルにつながります。
✅ 結論:
オイル交換ランプが点灯しただけではすぐにエンジンが焼き付くわけではありませんが、交換を先延ばしにすると確実にリスクが高まり、最終的には焼き付きに至る可能性がある、というイメージです。
私
ランプがついてどのくらい走れるものなの?
チャッピー
いい質問です 👍
「オイル交換ランプが点いてからどのくらい走れるか」は、実は車種やオイルの状態、走り方で変わります。
一般的な目安
- 数百 km ~ 1,000 km 程度なら、多くの車では致命的なトラブルには直結しません。
- ただし「安全に余裕を見て交換すべき距離」は できるだけ早め(数百 km 以内) と考えるのが現実的です。
なぜ「余裕」があるのか
- オイル交換ランプは「そろそろ交換してね」という“予告”であり、点いた瞬間にオイルがゼロになるわけではありません。
- 実際はエンジンやオイルの耐久性を考慮して、ある程度の余裕を持たせて点灯する設計です。
- 例えば:
- 通勤や買い物中心の軽負荷 → 1,000 km くらいは走れてしまうこともある
- 高速走行や高回転多用、ターボ車 → 早めに性能劣化が進み、余裕は少ない
リスクのある放置
- 長期間(数千 km 単位)無視 → オイルが劣化・粘度低下し、潤滑不良 → エンジン摩耗や焼き付きのリスク
- オイル減りがある車で放置 → 最悪の場合、オイル切れで即焼き付き
結論(実用的な答え)
- ランプが点いてから 数百 km くらいならほとんどの車で問題なし
- ただし、1,000 km 以上走るのは推奨されない(劣化は確実に進む)
- できれば「点いてからすぐ、次の給油や週末にでも交換」が安心
調べ物
修理の見積書にあった「エンジンASSY」ってなんだろう?
「エンジンASSY(アッシー)」は、自動車整備や部品販売でよく出てくる言葉です。
ASSY(アッシー)の意味
- Assembly(アッセンブリー) の略。
- 日本の整備業界では「ASSY(アッシー)」と表記されることが多く、
複数の部品をひとまとまり(ユニット)にしたもの を指します。
エンジンASSYとは
- エンジン一式をユニットで交換できる形にしたもの のことです。
- 中身はメーカーや整備工場の定義によって多少違いますが、一般的には:
- シリンダーブロック
- ピストン、クランクシャフト
- シリンダーヘッド(バルブ、カムシャフトなど含む)
- オイルパン
などを組み立て済みの状態でまとめたもの。
イメージとしては「エンジンの心臓部を丸ごと1個の部品として扱う」感じです。
部分修理との違い
- 部分修理
→ 例えばヘッドガスケットだけ交換、ピストンリングだけ交換など。 - ASSY交換
→ 細かい修理をせず、エンジン一式をまとめて交換。
→ 作業工数が減り、確実性が高い(新品やリビルト品が入る)。
→ ただし費用は大きい。
まとめ
- 「エンジンASSY」とは エンジンを構成する主要部品を一体でまとめたユニット品。
- 修理現場では「細かく直すよりエンジンASSYごと載せ替えた方が早い・確実」という場面で使われます。